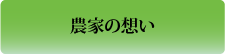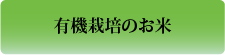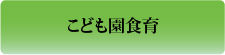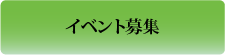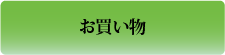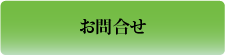稲刈の後、早ければ早い程いいのが、トラクターでの耕転があります。だから米ぬか散布しながら耕転の繰り返しか、先にすべて耕転するかの二者択一になります。大変な量ですが、土づくりには、時間と手間暇かけて行います。いい土作りはいいお米作りに直決すると信じています。僕の場合は、冬に土作りをします。来年も美味しいお米が出来ますようにと、祈りながら。出来ればくれ返しを月1回位したいのですが雨との兼ね合いです。今年は浅くすき込み、土を細かく耕転、これを最大目標にします。

春先にしなければいけない作業に、畦塗りがあります。昔の教えで、苗半作、水持ち半分という言葉があります。いい苗を作れは 半分成功したもの、水持ちがいい田んぼは半分成功したものと理解していいでしよう。トンネル工事専門のモグラが出没します。厄介者です。モグラ対策にも畦塗りは必要です。畔の間から水漏れ防止の為にも、畦塗りは必要です。タイミングは結構難しいです。雨が降った後1日~2日於いて行いますが、畦に石が多いと過負荷がかかり、機械が止まります。1反(10a)当たり30枚として25反(250a)でざっと750枚2か所の苗箱が入ります。培養土は無肥料です。750枚置く苗床がいります。均平された苗床これが難しいですよ。種蒔きしてから35日から45日後には田植えです。太い茎の苗で20㎝から22㎝位の長い苗作りを目標にします。今年は余り後ろを見ないで田植えをしたいと思い、2枚の大きなバックミラーを付けようと思います。ジャバジャバ代掻きをします。と言っても始めてです。土の高さの2倍位の水を入れ、土を細かく砕いて、トロトロ層を作ります7日から10日置いて再び代掻きを2回する予定です。その後数日置いて田植えです。去年とは違った方法でやりますから落ち度がないように細心注意を払いながら。

最大の悩み事は除草です。上手く行きますように。昨年から大きく作業方法が変わります。三木の自然農業の方の方法を採用します。秋の荒耕から代掻き迄すべてハローで耕転します。土を細かく細断、そして浅くと、コナギ対策が上手く行きます様に中耕除草機のロータも消耗して爪の補強もしないといけません。ツーアーム、テンフィンガーは正確ですが2町6反の除草は無理です。古希1年生には大きな負担です。昨年、中耕除草機2回かけましたが、7月初めから8月10日前後かかりました。辛い仕事です。有機農業の最大の欠点です。皆さんお困りです。又雑草は痩せた時の土、普通の土、肥えた時の土と、雑草は違って来ます。ある対策が、Aの圃場には有効だか、Bの圃場では無効と、当たり前なのです。有機栽培、皆さん肥料が違います。皆さん色々苦労されています。有機資材対応の物を使用しないといけません。価格が高いのが現状です。普及しない理由は、雑草対策ですよね。僕はそう思います。

除草が上手くいっても、土用干しをする、落水させます。その後、水を入れます。この水を待ち受けているのがヒエです。下手をすると全面ヒエのオンパレードに、なりかねません。ここを上手く乗り越え、稲刈り、乾燥、うす摺、出荷となります。一年で一番忙しい時です。昔から猫の手も借りたい言いますが、朝日いうお米栽培しまして、今食べていますが、結構おいしいです。お米のルーツと言われ、幻のお米と言われています。株も大きく分けつもいいです。大地の恵みに感謝、合掌もっともっと、伝えたい事ありますが。